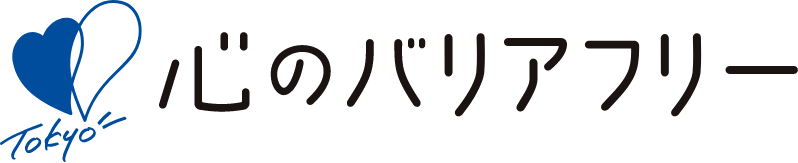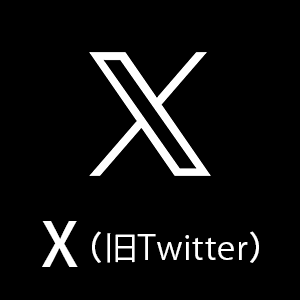〝人間どうし〟のつながりが心のバリアフリーには不可欠
- 声をかけるのは挨拶をするのと同じ
- 私は東京2020オリンピック・パラリンピックの時に組織委員として活動してきました。心のバリアフリーについては、こうした活動を通して事あるごとに考えてきたと思います。それでも普段の生活の中で、電車に乗ったりスーパーに行った時に困っている方を見かけて、声をかけるかどうか迷ったりすることがあります。声をかけることはできますが、自分でやりたいと思っている方もいるかもしれない……、自分がこのタイミングで声をかけてもいいのかな、と悩んでいる間に時間が過ぎてタイミングを逸してしまうこともあります。
- 子供が生まれて、ベビーカーで移動する時にエレベターが見つからず、階段を気合を入れて上ろうとした時に「手伝いましょうか?」と声をかけていただくことがあります。そんな時に自分が恥ずかしくて「大丈夫です!」と言ってしまう事があるんです。あとで「ありがとうございます」と、助けてもらっても良かったかな、と思うのです。その方は勇気を出して声をかけてくださったのかもしれないのに。初対面でも「こんにちは」と笑顔で挨拶をすることはできます。困っている方に声をかけるって、それと同じなんですよね。
- 声をかけるのに、勇気が必要な人もいれば、自然にできる人もいます。私自身はまだ、タイミングを見てしまっているところがあります。声をかける、助けあう、支えあうというのが当たり前の世界になっていくと、お互いに笑顔になれて嬉しいじゃないですか。コミュニケーションをとるきっかけは、人と人とが声をかけ合うことから始まるのだと思います。
- 私たちの思い込みが作るバリア
- 私はイベント等で車いすの体験をしたり、高齢者の方たちと体操をする機会が多いのですが、意外とおじいちゃん、おばあちゃんが体操をできるんです。一緒にするまでは、無意識のうちに高齢者だからという思い込みがあったのかもしれません。
- 障害を持つ方たちに対しても、無意識の思い込みがあるのかもしれません。そうした思い込みを少ずつでもなくしていくためには、経験できる、体験できる環境づくりというのが必要だし、身近にあればいいなと思います。特に教育の場にこうした環境が必要だと思っています。
- 例えば、点字ブロックは「目の不自由な方が通る道だから、ここに荷物を置いちゃいけないのよ」ということを教育の場で学ぶことができれば、子供たちは自然に、点字ブロックは「目の見えない人が通る道だから、自転車を置いていたら危ない、駄目なんだよ」ということがわかるようになります。もちろん、親として生活をする中で伝えていかなければいけない事だと思っています。子供は「なんで車いすに乗ってるの?」「歩けないの?」と聞くこともあると思います。そうした時にオープンに話すことが大事なのではないかと思います。車いすに乗っていることはマイナスでなく、「車いすがあるから、いろんなところに行ける」「車いすはすごいんだ」と、プラス思考で会話をすることが重要なのだと思うんです。そのためには家庭の中でオブラートにくるまずにわかりやすい言葉で説明をする。
- 私は電車でお年寄りの方が乗ってくると「どうぞ」と自然に席を譲るのですが、つい最近、娘もやっていたんです。「どこで覚えたの?」と褒めちぎったら、娘は「え~、ふつうだよ。私は立てるから、おじいちゃん、おばあちゃんは足が弱くなってくるから、座ったほうがラクなんだよ」って答えたんです。もしかしたら私のことを見ていて、真似っこしてくれたのかなって、プラス思考で考えているんです。こうしたことを親から子に自然に伝えることができたらいいなと、親になって実感しています。心のバリアフリーという言葉を使わなくても、家族で日常的にそうした話をする環境ができると良いですよね。
- 一日の出来事を振り返ってみる
- 最近、多目的トイレにベビーカーで入ったのですが、ドアを開けた時におむつのベッドが倒れていてぶつかってしまったんです。私は力があるので避けられましたが、もし車いすの方や手が弱い、力が入りにくい方が遭遇したら大変です。もしかしたら前に使用した人が急いでいたのかもしれませんが、元に戻すという心遣いや思いやりを広げたいですね。日常生活の中には経験しないとわからないことが、たくさんあります。経験すること、想像することから次のプラスアルファが生まれてくるのだと思います。
- 私はいつも一日が終わった後に、その日の出来事を振り返って、自分がやってもらって嬉しかったことが今日は何個あったかなと考えて書き出しています。時間が無かったら考えるだけでもいいんです。例えば、ベビーカーを電車から降ろす時に、隣の人が通路をあけてくれるとちょっと嬉しいじゃないですか。自分がやったことより、やってもらったことって何だったかな~と考えた時に、やってもらって嬉しかったことを吸収したい……日常の中で小さな嬉しさや楽しさ、幸せがいっぱい増えれば、心のバリアを取り除くことにつながっていくと思うんです。
- パラアスリートとの交流
- 東京オリンピック・パラリンピックを通して多くのパラアスリートと交流してきました。パラリンピックの選手たちは自然体で私たちと一緒に行動してきました。パラアスリートと会う前から、どのように接したら良いか、どのようなサポートをすれば良いかを考えていた自分が本当に情けなく反省することが多かったです。もちろんそれぞれ個性はありますが、オリンピアン、パラリンピアンの区別をすることなく、みなさんは普通にコミュニケーションをとっていました。車いすに乗っていたとしても、車いすは体の一部と一緒で足の役割をしている。車いすだから大変とか、そういう感覚は全く感じませんでした。そうしたことも、会話をし、コミュニケーションをとらなければわからなかったので、コミュニケーションは本当に重要だということを実感しました。
- 東京オリンピック・パラリンピック後では環境づくりも含め、だいぶ変わってきたのではないかと感じています。合宿やイベントなどもオリンピックとパラリンピックを合同ですることも増えました。
- 日本で開催する大会であれば、イベントをプラスしてオリンピアン・パラリンピアンの方々が出る試合が増えてもっと盛り上がっていったらいいなとは思っています。元アスリートとしてさまざまな面での環境づくりに力を入れていかなければと感じます。
- 障害者、健常者の区別はない
- 「心のバリアフリー」はすべてのことに当てはまる言葉だなと思います。実は、若い頃の私は障害のある方々に声をかけることがずっとできなかったんです。なぜかというと「自分の助け方はあっているのか?」と考えてしまい、見て見ぬふりをしてしまった自分がいました。これこそがバリアだったんですよね。東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会で理事をさせていただいて、いろんな方々と出会いお話をする時に、周囲にバリアを感じていた昔の自分がとても恥ずかしくなりました。障害者、健常者を区別するのではなく、「手伝いが必要な人、必要でない人」と考えれば、断られてもOK。こうしたことも経験をさせていただいたからわかったことです。
- イベントなどで、オリンピアン、パラリンピアンがゲストとして登場した時、「みんなでイベントを盛り上げよう!」という空気があり、そこにはバリアはありません。東京オリンピック・パラリンピックは日本全体が変わっていく一つの機会だったと思います。選手だけでなく、ボランティアの方々も東京オリンピック・パラリンピックを経験したことでいろいろな発見ができたのではないかと思います。
- 「特別」ではなく「当たり前」にしたい
- 車いすバスケットを経験させてもらった時に、私たちは足を使っていたのに、上半身だけでプレーする方たちに全くといっていいほど歯が立たず、パラアスリートの凄さを改めて感じられる機会がありました。どこを使っているのかと聞くと「肩甲骨ですよ」という答え。彼らはすごいアスリートなんです。確かに体操でも、選手が吊り輪の時に腕で止まっているように見えますが、実は肩甲骨で止まっているんです。一緒なんですね。そういう考え方を新たに知ることができました。
- 日本と海外を比較した時、海外はバリアが少ないと感じます。日本はまだまだ特別視する傾向がありますね。ロンドンオリンピックに参加させていただいた時も、コミュニケーションの取り方は、障害者、健常者ということは関係ないんです。その時点ですでにバリアがない。私は東京オリンピック・パラリンピックの理事になった時に、その経験や思いを伝えました。私たちだけでなくボランティアも含め、街全体でオリンピック・パラリンピックを作り、応援したくなる環境づくりについても話し合いました。心のバリアフリーという言葉を聞いて、気づかされる人はいっぱいいると思います。それでもやっぱり「わからない」とマイナスに考える方は多いので、少しでもプラスに考え、それが普通になればいいなと思うんです。
- 家族で今、田中体操クラブを運営しているのですが、ここにはほかのクラブには入れなかったお子さんも参加しています。体験に来られるお母様から、「子供に経験を積ませたいんです。大丈夫でしょうか?」と聞かれることもあります。私はここでいろんな人たちと交流することで、たくさんの経験をしてもらいたいと思っています。